追章 強者
<1976年9月24日>
2年間、共に生活
沢田研二はぼくにとって、どのような存在だったのか。ある種の結論を出さないとこれからの日々は乗り越えられないような気がする。
オーバーな話ではなく、この9か月、彼の影がふとした時にもついてまわった。企画1年、打合わせなどの期間を入れると、2年間もぼくは沢田と生活していたことになる。
「ザ・スター沢田研二」のタイトルに一瞬とまどったのは沢田研二だった。スターという呼び名は過大評価ではないかというのだ。しかし彼が本来のスターとしての条件や自覚をきびしくみすえたとしても、あまたのファンやマスコミの目からみれば、沢田はスター以外のなにものでもなかった。
この矛盾を含みながらぼくらは話しはじめた。
スターという箱の中で人間としての自我の限界、それは永遠のテーマだった。二度の不祥事がテーマを一層リアルにした。
1ヵ月の謹慎が明けた翌日、ぼくらはしたたかに酔った。ある年配の業界記者の方が沢田にさとしたいという話が気になった。
「名のある芸人さんは汽車に乗るにも目立たない服をつけ、席をすみの方に、目線は正面より下に向けてじっとしている」
そこには芸人が人間としての権利が与えられなかった暗い時代的背景がにおった。沢田はめったにサングラスを使用しない。車も助手席が好きだ。日ざしに近い所にいたいと思う。
全国縦断に同行したぼくの目からみても、ホテルの一室にとじこもりっぱなしの沢田では、その日ざしを望むのは無理だった。
だからステージのフルライトが沢田にとって、唯一の光だったのかもしれない。沢田は光を投げかけるスターというならば、それは観客席から光をうけて反射する鏡だった。
スターは、おのれが発行体になり得ない。すべてまわりの光を受けて輝く。久世光彦さん(TBSプロデューサー)がいった沢田をみるファンの熱度というのも、ぼくのいう光と同意語に感じる。まず沢田をみるぼくらが光にならなければ。
言葉を選び抜いて
沢田は寡黙だった。うっかりした言葉は決してはかなかった。実に注意深く言葉を選び抜いた。ニッポン放送のDJを担当していた沢田は、軽快なテンポでしゃべりまくるのがぼくには不思議なことだった。
「あれが本当のぼくのしゃべりなんですよ。問題を決定づけたり、思い込んだりするのは好きじゃない・・・・」
よく聞けばすべてフォーカスアウト風な、ほどよいいい方で済まされていた。本音をひとつはずした方が沢田としても楽だったし、深刻なDJなどうけるはずもなかった。
だが沢田に本音がないわけがなかった。
問題を提起する。沢田は言葉をのみこむ。もう一度問題をつきつめる。すると5分ほどかかって苦痛にも似た短い言葉がかえってくる。
沢田の一枚々々がはがされて、やがて彼はぼろぼろの裸になるのではないかと、まわりの人は恐れた。ついに沢田は自分の姿を露出して、自分のいった言葉に縛られながらも、この9ヵ月の日々を暮らしていったことになる。その日々の中で起きた小さなアクシデントが今も残る。
二度目の不祥事が起きた直後で、事実経過をすっかり沢田から聞き終えて、ぼくらが深夜のスタジオから外へ出た時だった。彼を心配そうにみつめるファンが裏門をとりまいていた。その人ごみをわけながら、アスファルト通りに出た直後、勢いよく走ってきた一人の女性と突き当たり、沢田は右肩を飛ばされるようによろめいた。
「・・・・すみません」
おもわず小さな声をあげてあのは沢田だった。たったいまカセットテープに入れたばかりの沢田の自我が、ぼくの頭の中で音を立てて壊れた。
不祥事と呼ばれても守らなければならない怒りの自我、確認したばかりのその言葉と行為が瞬間すれちがった。反射的に沢田は引いてしまったのである。
“対等”でありたい
常に相手と対等でありたいと望む沢田、しかし彼はスターとして特権的優位な立場に立つよりも、スタートして弱者に立つ場面の方がやはり多かった。
沢田をたたいて弱者にしようとする者には、彼は毅然と戦っていくだろう。だがなにより弱者にするのは沢田自身の胸の中にひそむ敵ではなかったろうか。ふるい立ったように沢田は、ぼくのまえに強者への願いをさらしていったような気がする。

ザ・タイガースが解散し約5年、話が来た時、結婚もし、一区切りということでこうやってじっくり今の自分の心境を述べることもいいかもしれないと思われたのかもしれませんね。当時をリアルにもちろん知らない私にとっては貴重な資料です。この機会を設けていただき、ありがとうございました。
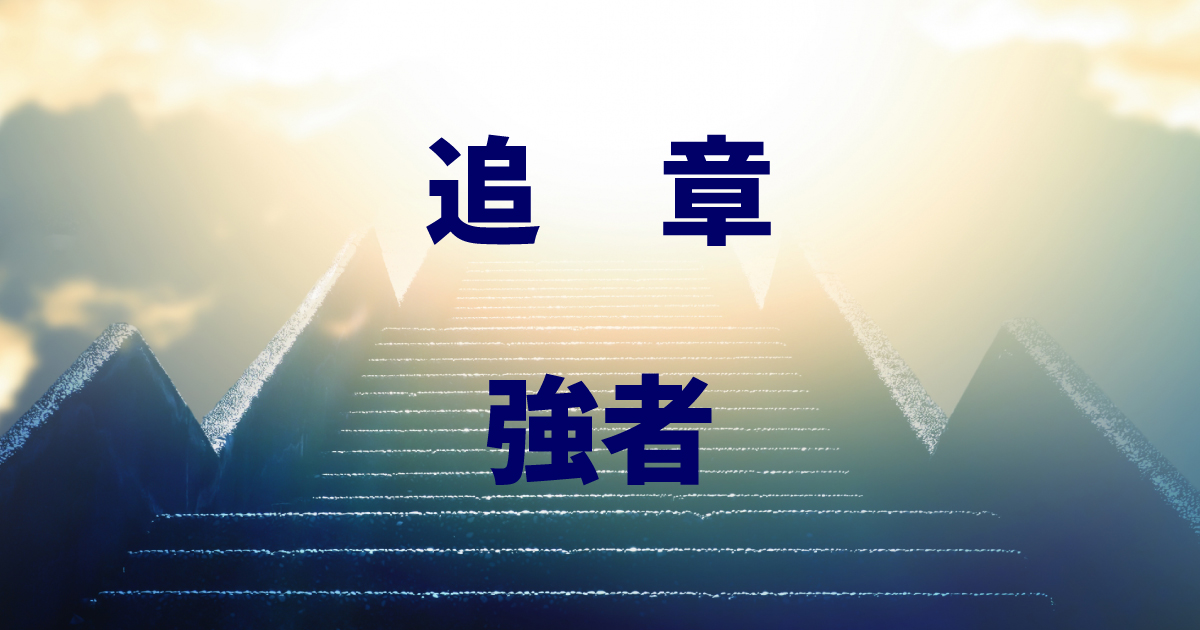


コメント