第19章 遊び
話した人 沢田 研二<1976年5月21日>
はて何だろう
自分のことを無趣味なヤツだと思っている。だからあれをしてこれをしてという遊びに対する具体的な夢はもっていない。人に誘われるままに競馬、釣りとさわってはみたが、のめり込むまでは至らなかった。
それじゃ休みの日には何をやっているのかといわれるが、仕事から仕事への体力調整の期間だったりする。だからその間、体を休めるのは遊びではなく、仕事のうちだとも考えられる。
そうしてみるとたまに野球をしたり、酒を飲みに出かけるのが、せいぜいぼくの遊びなのかな、とにが笑いしてみる。酒を飲みにいくのも、仕事とオーバーラップすることが多い。打上げパーティーだとか、仕事の前祝いだとか、なにかと席を設けられることも多い。
だが打合わせまで、この席でやられるのはまずい。酔った勢いで、話はうまい酒の肴をを選ぶように、どんどん勝手な方向に進む。さめてから覚えていないじゃすまされない。酔って気が大きくなるのは責められない。誰しも弱い心を酒で無理に強くする時もある。うかつな仕事の話はしてはいけないのだ。自分では酒に飲まれない自信があったとしても・・・・・。
”芸人は遊ばなくてはいけない”この言葉をあえて昔の時代だといってしまおう。
お茶屋さんにあがったり、芸者衆になじんだり、今は無縁なことである。それにかわる飲む、打つ、買うが現代にあったとしても、この情報時代にスキャンダルをふりまくだけである。いったい遊んだかわりに手に入れられるものといったら何があるのだろう。
たまには特別な芸人の世界から足を伸ばして、街中の日常生活をかいまみなければならない、芸の材料は人間味あふれる生活の中にある、つまりはそういった価値観、意味なのではないだろうか。
理屈は、いらぬ
たとえばぼくはいまとんかつ屋でエビフライを食べている。カウンター越しにコックさんのキャベツをきざむ姿がみえる。包丁さばきひとつにしても、彼の人生がうかがえる。薄さ2ミリにキャベツをきざむ指にぼくとちがった生き方がある。他人を知ることは遊ばなくても出来る。
いわゆる芸人の遊びには、イキだヤボだがつきものである。はたして遊びにイキもヤボもあるのだろうか。ぼくにはわからない。遊びはしょせん遊び、それ以上に理屈をつけて楽しいことはない。
遊び人と称される人は、何をして遊んでいるのだろう。たぶん真剣に遊んでいるのだろうが、それは遊びを仕事としたスペシャリスト、かなりヘビーな人生であろう。
子供の頃の遊びといえば、日暮れ近くまで外を走りまわって解放感にひたることだろうが、思春期ともなると何か刺激的な胸のたかなりを覚えるような未知の物に手をふれたくなる。その未知の物に少しばかり悪い香りが漂っていたりすれば、いっそう少年の心は熱くなる。好奇心である。
授業をさぼって喫茶店に入ったり映画を見たり、タブーを犯すことにときめきを感じる。世の中でいわれているタブーは本当なのかと考えてもみる。ぼくも中学時代にはいろんな遊びをためしてみた。かなりお金をはり込んで友達とキャバレーの門をくぐった時の興奮は忘れないだろう。
ただしひとつだけわきまえていたことがある。自己のタブーは犯しても、他人の領域は犯してはならないということ。ケンカして注意を受けることはあったにせよ、こいつだけは肝に銘じていた。
ボク、放蕩?
放蕩息子といつたいい方がある。ぼくらが音楽に関心を持ちだしたのはエレキブームのはしり、アンプから電気音を発して喜んでいる少年は、いぶかしい目でみられた。いわんやその音楽で身を立てるなどといったら、放蕩息子呼ばわりされたにちがいない。
若者が自分の夢を追い求める時、その夢の世間のとらえ方ひとつで、さまざまな評価を受ける。だが、もっと心強く飛べ。もしかしたら放蕩息子とは、自分の生き方をみつけたすばらしい男をいうのかも知れない。
遊びとは余裕、ゆとりでもある。自動車のハンドルのあまりを遊びというのに似ている。スケジュールに追われているといっても結構時間はあるものだ。
しかしこの時間をぼくはうまく使いこなせていない。きちんとあまりの時間を使いこなせるようになって、はじめてゆとりと呼べるものが出来るのだろうに。ただ無意味な時間が流れているのをゆとりとは感じない。
金とヒマがなければ遊べないという。ぼくは不現実なことは考えない主義である。
遊びのために金をため、ヒマを作ることもない。何かを犠牲にして生みだす遊びは、ぼくにとってムダなことにも思える。ふっと日常の中で空間が出来た時に、さらりと楽しんでしまうような、そんな何げない遊びが好きだ。
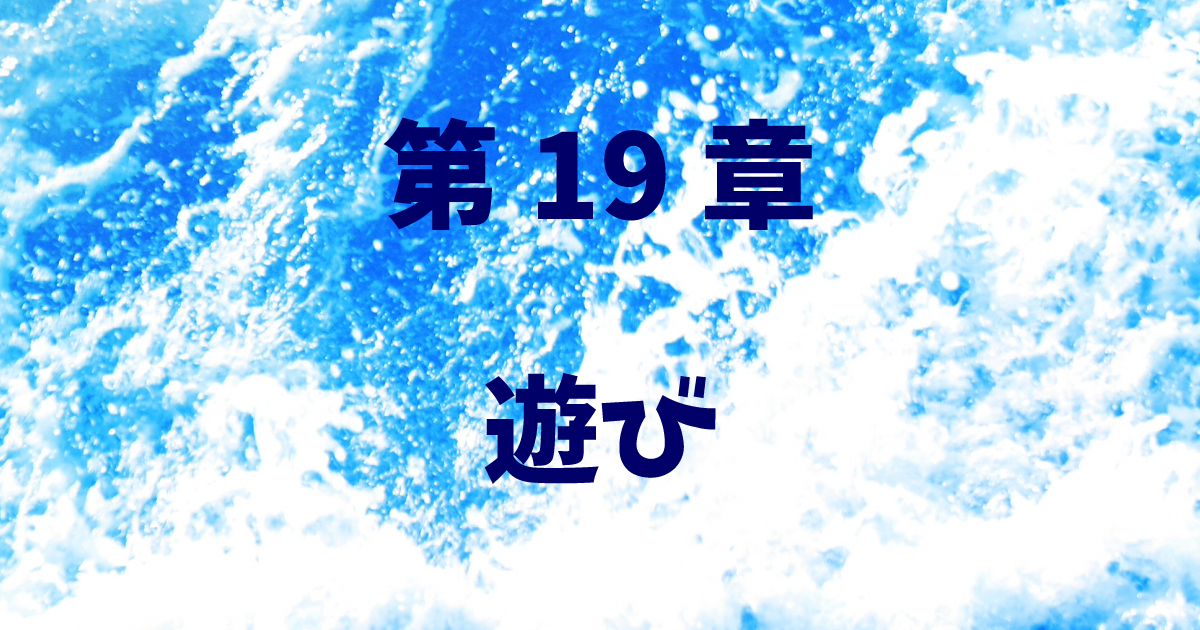


コメント